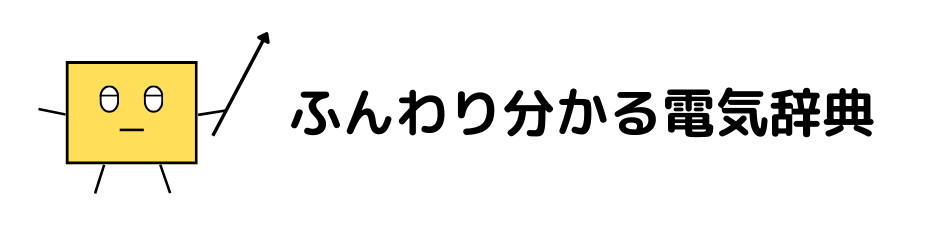ASICの用語解説
- 特定の用途向けに特化したICのことだよ
- 電子回路のコストや基板サイズを減らしたいときに役立つよ
- 設計するのにけっこうなお金がかかるよ
一言でいうと
ASICとは
ひとつの製品とか用途だけにつかう前提で、必要な機能をぎゅっとつめこんだICのこと
です。
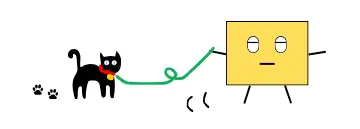
詳しい説明
順番に説明していきましょう。
まずは予備知識として、ICのことに触れておきましょう。
最近の電子基板には、ICがけっこうたくさん使われています。
メモリーとかCPUとかの、デジタル信号をつかって計算&保存するものはもちろんのこと、
オペアンプとかA/Dコンバーターといった、アナログ回路を一つのチップにつめこんだものもあります。
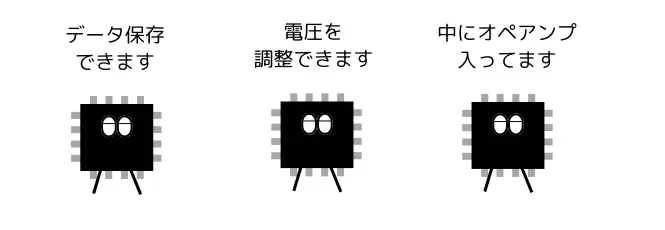
このICはいろんなメーカーがいろんな製品を作って販売しています。
なので、電子基板の設計者としては、欲しいICをちょいちょい買ってのせれば、簡単にほしい機能を持たせられるんですね。
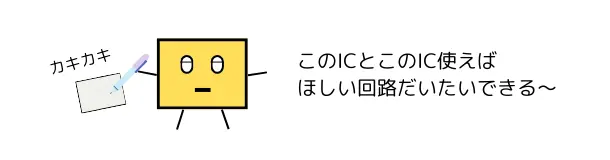
じゃあ、なんでASICがいるの?という話に進みましょう。
ここまでのように、普通に電子回路を作るだけなら、そのへんで売っているICを使えばだいたいのものはできます。
ただ、
「もっとコスト下げたいぞー!」
とか、
「基板もっとちっちゃくできないの?」
みたいな要求が来ると、普通に作るだけだとどこかで限界がきます。

そこで、一つの選択肢になってくるのがASICです。
ASICなら「うちの基板向けにぴったりなIC」が作れます。
なので、「このICとこのIC、あと周辺回路をぜんぶひっくるめて一つのチップにする」みたいなことができるんですね。
そしたら部品の面積が減るので、基板をよりちっちゃくできますし、
大量生産するならチップ自体のコストも下げられます。
ただ、ASICは一回設計するのにけっこうなお金がかかるので、
「やっぱりこっちの回路に変えたい!」
みたいなのは気軽にできなくなる点に注意ですね。
余談ですが、
「ほかの企業にうちの回路を見せたくない!」
という場合にも、ASICが活躍したりします。
市販のICやディスクリート部品(抵抗とか)を使っていると、製品を取り寄せて基板を見れば、どんな回路構成か分かっちゃうんですね。
(これをリバースエンジニアリングとかいいます)
それだと頑張って設計した企業はこまっちゃうので、回路をまるごとASIC化して対策します。
ASICだと、かんじんの回路がぜーんぶICの中に入っちゃってるので、調べたくても調べられないという訳ですね。
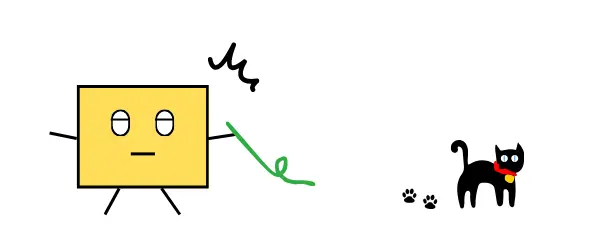
最後にまとめるよ
つまり「ASIC」という名前を聞いたら、「特定の用途や製品にぴったりの機能をつめこんだICのことなんだな~」と思っておいてください。